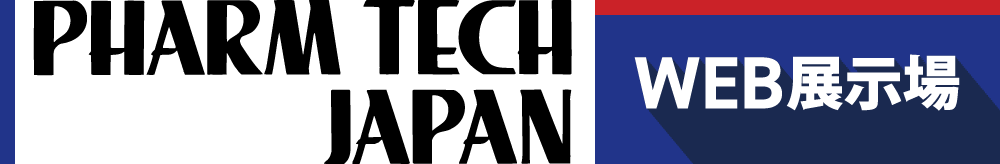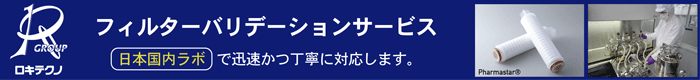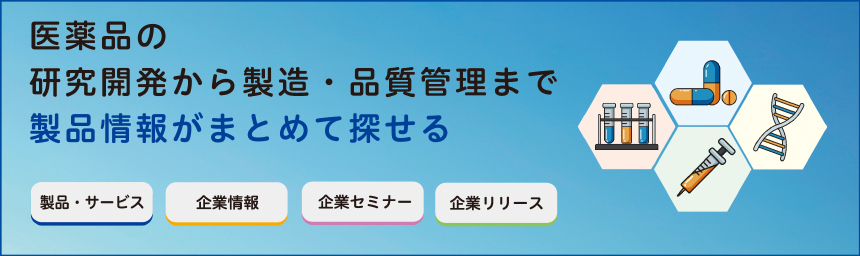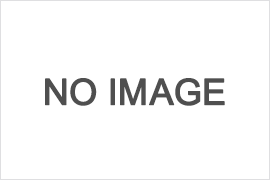キーワードから探す
カテゴリから探す すべてのカテゴリを見る
原薬・添加剤・中間体
製造機械・装置
物流・輸送
プロセス測定・検査
ラボ用測定・分析
滅菌・クリーン
供給・搬送
プラント・設備
包装関連
受託サービス
バイオ(抗体)医薬品
ITソリューション
コンサルティング・翻訳・その他
WEB展示場に出展中の企業・製品情報
注目の出展製品 すべての製品を見る
WEB展示場 出展企業 すべての企業を見る
【AD】日本のバイオ製薬業界の展望を拓く 進化し続けるグローバルCDMOの役割
日本のバイオ製薬業界は、がん免疫療法、抗体薬物複合体(ADC)、次世代バイオロジクス分野の進歩によって急速に変貌しつつある。規制要件がさらに厳しくなり、高付加価値な治療法へのニーズが高まっていること ...続き 2025/04/14
【AD】世界標準のLIMS「LabWare」 98%の満足度評価が示す実力を探る
世界最大規模のLIMSベンダーであるLabWare社。1987年の創業時からLIMS開発に着手し、世界125カ国2500社以上への導入実績を誇る。わが国においてもLabWareを採用する企業が急激に ...続き 2025/04/22
【AD】データインテグリティ対応プラットフォーム「zenon」 ~製薬工場のデジタル化、Pharma 4.0実現へ強力サポート~
■日本法人設立で、現地サポート強化・サービス拡充 COPA-DATA Japan株式会社が2024年7月、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションに特化した独立系ソフトウェアメーカ ...続き 2025/04/25
【AD】DIを確保しながらGMP記録の電子化を強力に支援 PDF専業メーカーとして、使いやすさを追求
近年、データインテグリティ(DI)への対応や業務の効率化・省力化の観点から、医薬品製造現場の電子化が進められている。MESやLIMSを利用して電子化が進められることが多いが、それらへ取り込みにくく、 ...続き 2025/05/07
【AD】デジタル技術で医薬品工場に命を吹き込む 20名の先鋭スタッフが安全で効率的な医薬品製造をトータルサポート
大手ゼネコンの大成建設は、医薬品製造の安全かつ効率的な生産を実現するため、情報技術専門チーム「デジタルファシリティソリューション室」を設置し、医薬品製造現場のデジタル化に貢献してきた。ゼネコンのエン ...続き 2025/05/12
ファームテクジャパン2025年5月号のみどころ
●特集医薬品製造/試験における電子化・新技術活用とデータインテグリティ 5月号では医薬品製造および試験におけるデジタル技術の活用とデータインテグリティ(DI)について特集しています。近年、医薬品製造現 ...続き 2025/04/28