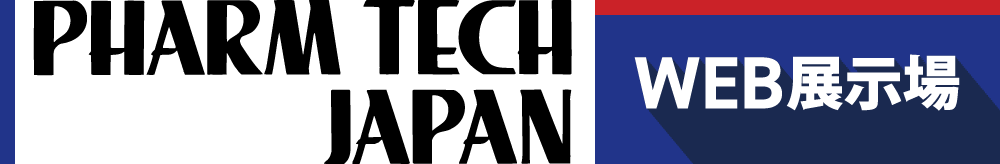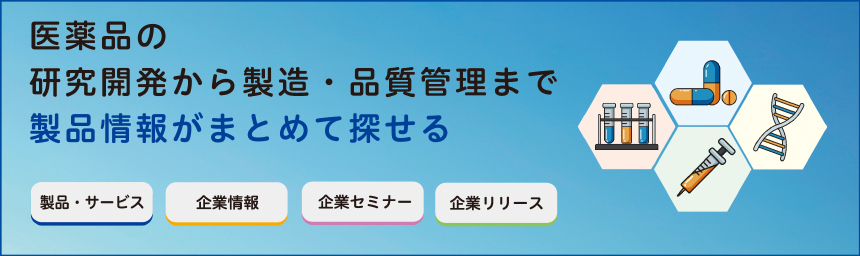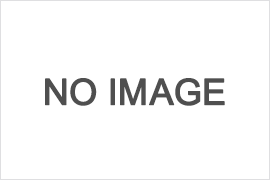キーワードから探す
カテゴリから探す すべてのカテゴリを見る
原薬・添加剤・中間体
製造機械・装置
物流・輸送
プロセス測定・検査
ラボ用測定・分析
滅菌・クリーン
供給・搬送
プラント・設備
包装関連
受託サービス
バイオ(抗体)医薬品
ITソリューション
コンサルティング・翻訳・その他
WEB展示場に出展中の企業・製品情報
注目の出展製品 すべての製品を見る
WEB展示場 出展企業 すべての企業を見る
最新業界トピック(ニュース記事の閲覧には会員登録【無料】が必要です。)
- 第15回富山県GMP講演会 QAは品質の本質を理解し、経営陣へのアプローチは「伝わる言葉で」 2025/12/24
- 塩野義、田辺ファーマからエダラボン事業を買収 総額25億ドルで 2025/12/24
- 旭化成ファーマ、グローバル研究開発拠点を湘南アイパークへ移転 2025/12/23
- 製剤機械技術学会、Annex1分科会開催 工場見学を通じた実践の学びも 2025/12/23
- かきくけこらむ 目標と方針 2025/12/23
- NPO-QAセンター 創立22周年セミナー 2025/12/23
- 第5回GMPラウンドテーブル会議 PMDA、リスクコミュニケーション活動について「本質的な価値を提供できているかを常に自問」 2025/12/22