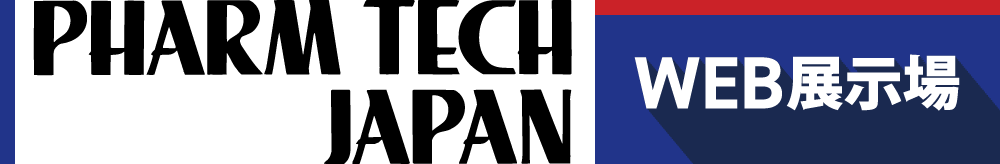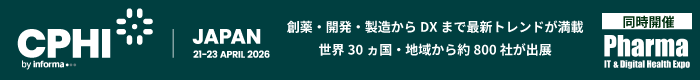| 開催日 | 2026年2月6日(金) |
|---|---|
| 開催地 | Web |
★世界最先端のメディカルライティングに関連するAIの動向や、医薬品開発文書作成における生成AI使用の具体例が学べます!
■セミナーテーマ
メディカルライティングにおけるAI活用の具体例
■講師
合同会社クリニカルランゲージ 代表 山本 隆之 氏
個人翻訳者
■経歴
医薬分野の翻訳者。東京外国語大学外国語学部卒業。
大学卒業後、自動車部品メーカーや電機メーカーで営業・マーケティングなどを担当。一方で医薬翻訳に興味を持ち、通信講座で翻訳の勉強を始める。2016年より、CRO(医薬品開発業務受託機関)で安全性症例報告(CIOMS)の翻訳およびQCを担当(英訳がメイン)。2017年、米国シカゴ大学Medical Writing and Editing Certificateを取得。2019年より、フリーランス翻訳者として医薬品開発文書(プロトコル、治験総括報告書、CTD、同意書、照会事項、症例報告など)の翻訳(主に日英翻訳、機械翻訳のポストエディットも含む)に従事。医薬翻訳(日英翻訳)に関するセミナー講師なども担当。
■専門および得意な分野・研究
・医薬品開発文書(プロトコル、治験総括報告書、CTD、同意書、照会事項、症例報告など)の日英翻訳(ポストエディットも含む)
・医薬分野AI翻訳サイトを個人開発
・医薬翻訳の日英翻訳やポストエディットの方法についてセミナーやnoteで発信
■本テーマ関連の公的委員及び専門学協会等での委員会活動
日本翻訳者協会(JAT)会員。JAT主催の国際会議IJET32トロント(2024年5月)では「翻訳におけるChatGPTの活用方法」について講演。JATの製薬翻訳分科会JATPHARMAでは、医薬翻訳英訳における機械翻訳(MT)ポストエディットの方法についてセミナーを実施。
日本翻訳連盟(JTF)会員。米国メディカルライター協会(AMWA)会員。
●日時:2026年2月6日(金) 13:00-15:30 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
■講座のポイント
医薬品開発や医療分野では、AIを活用した業務の効率化、高精度化が様々な領域で進められています。メディカルライティングもそうした分野のひとつであり、AIを有効に活用することが求められています。
本講座では、国内・海外でのメディカルライティングに関連するAIの動向、生成AIを使用する際に必要となるプロンプトの書き方の基本を学び、実際の医薬品開発文書における生成AIの活用方法の例や注意点をご紹介いたします。
■受講後、習得できること
・世界最先端のメディカルライティングに関連するAIの動向を学べます。
・生成AIに指示を出す際に必要となるプロンプトの基本的な書き方を学べます。
・規制当局(FDA、EMA、PMDA)のAI使用に対する考え方の概要を学べます。
・生成AI使用時の注意点と、医薬品開発文書作成時における活用事例を学べます。
■講演プログラム
1.AIの現在と国内外での動向
1.1 AIの歴史
1.2 生成AIの登場
1.3 様々なLLM(ChatGPT、Gemini、Claudeなど)
1.4 海外での動向
1.5 国内での動向
2.メディカルライティングにおけるAIの動向
2.1 海外規制当局の考え方
2.2 欧米メディカルライターの考え方
2.3 国内でのメディカルライティングにおける動向
3.生成AI活用時に必要となるプロンプトの基本
3.1 プロンプトの役割
3.2 基本プロンプト(コンポーネント)
3.2.1 ペルソナの設定
3.2.2 指示(Task)
3.2.3 背景情報(Context)
3.2.4 出力形式(Format)
3.3 few-shotプロンプト
3.4 その他の改善ポイント
4.医薬品開発文書作成時のプロンプトの例
4.1 症例報告(データから経過文の作成)
4.2 文体変更①:プロトコル→CSR
4.3 文体変更②:プロトコル→ICF→アセント
4.4 表→文章の作成
4.5 フォーマットに従ったデータの要約
4.6 スタイルガイドの適用
4.7 サンプルテキストを使用してスタイルを決める
4.8 要約・翻訳
4.9 プレインランゲージサマリーの作成
4.10 背景・開発の経緯セクションの記述
4.11 その他の精度を上げる技術(RAG、ファインチューニングなど)
5.責任あるAIの活用
5.1 注意点(セキュリティ、ハルシネーション、個人情報、著作権など)
5.2 認知負債
5.3 AIの利点と限界
5.4 信頼できるAIの活用へ
5.5 AIと人間の役割分担
(質疑応答)