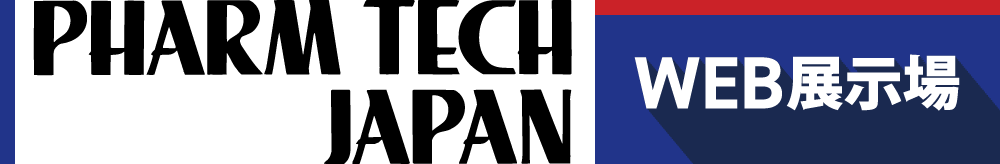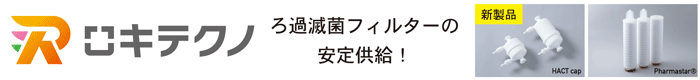| 開催日 | 2026年1月30日(金) |
|---|---|
| 開催地 | 東京都 |
☆待ったなしの生成AI時代を勝ち抜くための実践ノウハウを4時間速習!
☆最近話題の‘バイブコーディング’を含めて、明日から使える知識を丁寧に解説いたします!
☆臨床開発・治験関連業務をご担当の方はもちろんのこと、
ヘルスケア領域での最新情報収集といった用途でのご参加も大歓迎です!
※本セミナー実施にあたり、各自‘PCのご持参’をお願いしております。(会場にWi-FIがございます。)
※開催日が近づきましたら、事前にご準備いただきたい内容をメールいたします。
【テーマ名】
臨床研究/治験関連業務に生成AIをどう活用できるか?
―プロンプトエンジニアリングとバイブコーディング―【PCハンズオン研修】
【講師】
大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 臨床研究センター
副センター長/特任准教授(常勤)
浅野 健人 氏
慶應義塾大学 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター 教育研修部門長・広報部門長
慶應義塾大学病院臨床研究監理センターライセンス教育部門長
特任講師 博士(精神・神経科学)
吉田 和生 氏
※希望者は講師との名刺交換が可能です。
●浅野 健人 氏●
【学歴】
2002年 大阪大学医学部保健学科 卒業
2004年 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 修了
【職歴】
2004年4月~2013年8月 株式会社アイロム
2013年9月~2017年12月 高知大学医学部附属病院 次世代医療創造センター 特任准教授
2018年1月~現在 大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 特任准教授
【専門および得意な分野・研究】
・治験DX
・スタディマネジメント
・研究倫理
【本テーマ関連学協会での活動】
・日本臨床試験学会
・日本臨床薬理学会
・DIA
●吉田 和生 氏●
【経歴】
2007年3月 徳島大学医学部 卒業
2007年4月~2009年3月 独立行政法人国立病院機構東京医療センター(初期臨床研修)
2009年4月~2011年3月 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 専修医
2011年4月~2013年3月 医療法人財団厚生協会大泉病院
2013年4月~2017年3月 慶應義塾大学大学院医学研究科 博士課程(精神・神経科学専攻)
2017年3月~2020年5月 Postdoctoral research fellow: Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada
2020年6月~2022年2月 Clinical fellow: Department of Psychiatry, University of Toronto
2022年3月~2023年9月 Postdoctoral research fellow: Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada
2023年10月~ 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター教育研修部門長/特任講師
2023年11月~ 慶應義塾大学病院臨床研究監理センター ライセンス教育部門長
2024年4月~ 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター 広報部門長
【専門および得意な分野・研究】
・精神科分野
・臨床精神薬理分野
【本テーマ関連学協会での活動】(所属学会)
・日本精神神経学会(専門医、指導医)
・日本臨床精神神経薬理学会(評議員)
・日本神経精神薬理学会
・日本遠隔医療学会
・American Psychiatric Association
・American Society of Clinical Psychopharmacology
【開催日時】
2026年1月30日(金) 12:30-16:30
【会場】
[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室
https://johokiko.co.jp/access/kyurian/
【受講料】
1名46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
※詳細な内容やお申込み要領等は、下段「セミナーホームページを見る」をご参照ください。
【セミナーの内容】
■講座のポイント
本講座では、臨床研究や治験業務における生成AIの実践的活用を体感できる。前半はプロンプトエンジニアリングを扱い、問いの設計次第で生成AIからの出力がどう変わるかをハンズオン形式で学ぶ。後半は近年注目される「バイブコーディング」(生成AIとの会話を通じて感覚・ノリ(vibe)でアプリ等を構築する手法)を取り上げ、実際に自身の業務課題をもとに簡易アプリのデモ版を開発してみる。生成AIを業務でどう使えるかの具体的なヒントが得られる構成である。
■受講後、習得できること
・業務に即したプロンプトを設計し、生成AIの出力精度を高めるスキル
・臨床開発・治験業務における生成AI活用の具体的なユースケースの理解
・ノーコードでAIアプリ(例:報告書作成支援など)を試作する実践力
・バイブコーディングの基本概念と業務応用への展開方法
・AIを“ツール”ではなく“思考のパートナー”として活かすマインドセット
■本講座の想定受講者様
生成AI(ChatGPT等)を日常業務で使うこともあるが、イマイチ扱いきれていない/最近、触ることが減っている実務者。
■本講座受講のためにご準備いただくこと
・ノートPC
・ChatGPTのアカウント作成(無料版で可)
・GoogleAIstudioのアカウント作成(Googleアカウント使用可能)
※開催日が近づきましたら、お申込みいただいた方へ、リマインドメールをお送りいたします。
■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP:Good Clinical Practice)
・医薬品医療機器等法(薬機法)
・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
・日本製薬工業協会(JPMA)による「生成AI利用に関する留意点」などの業界指針
■講演中のキーワード
・生成AI
・プロンプトエンジニアリング
・バイブコーディング
・ChatGPT医療活用
・ノーコードAI開発
■プログラム項目
1 オープニング
2 導入講義
2.1 生成AIの要点、注意点
2.2 使用ツールの1分デモ
3 ハンズオン① プロンプト・エンジニアリング
3.1 基本テク
3.2 個人演習
3.3 共有
4 ミニ講義:AIエージェント/バイブコーディング概観
5 ハンズオン② バイブコーディング
5.1 仕様宣言テンプレ配布
5.2 演習
5.3 ライトニングデモ
6 落とし込みワーク
6.1 明日やる1手の決定
6.2 リスクと対応
7 クロージング
7.1 まとめ
7.2 質疑応答