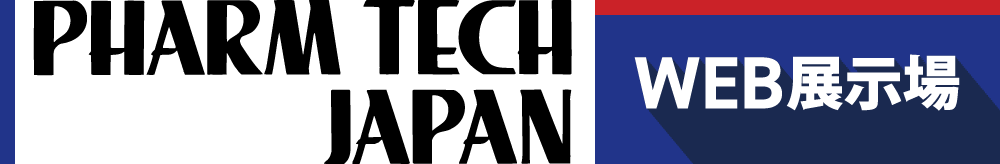| 開催日 | 2025年11月14日(金) |
|---|---|
| 開催地 | Web |
★今や開発者・技術者に必須のスキルとなったアイデア発想力の養成講座!
実用的な多くの発想法を示し、豊富な実例・実習も交えわかりやすく説明します!
開発者・技術者のためのアイデア発想法(実習付)
-生成AIの活用など新発想法を含む各手法と取りまとめ方など-
<講師>
フルード工業(株) 執行役員 研究開発室長
鹿児島大学 非常勤講師 工学博士・技術士(機械) 小波 盛佳 氏
<日時>
2025年11月14日(金) 10:00-16:30
<形態>
Zoomオンラインセミナー
<受講料>
【オンライン受講】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき41,800円
*受講料やセミナー申し込み~開催までの流れなど、詳細については、弊社HPのセミナーページを必ずご確認ください。
<セミナーポイント>
AIやIoTなどに伴う激しい変化に対応するために、開発や設計技術を新しい発想で切り開く時代です。課題解決はもちろん、問題を発見する力、さまざまな選択肢や可能性を創造する力が必要です。今やアイデア発想法は、テーマの探索・創出や特許発明のシーンなど応用範囲は多岐にわたり、開発者・技術者に必須のスキルとなっています。
アイデアを創出する力は訓練できます。本セミナーでは、講師が自ら発想し、開発・設計・実施に活かしてきた経験を基に、実用的な多くの発想法の紹介から実施に至るまでの流れと実行方法を示します。
まず、創造のための流れについて学びます。次に発想のツールであるマンダラートやマインドマップといった汎用的な発想法や、ロジカルシンキングの基礎を概説します。ヒントによる連想を促すTRIZ法やオズボーンのリストには、それを利用した多くの具体例を挙げます。さらに単位洗い出し法、動詞・形容詞連想法など、講師が学会で発表した新発想・連想法も提示し、実例を豊富に挙げてわかりやすく説明します。
実習では、アイデアを絞り出す感覚をつかみます。その発想から実現可能なものに絞り込んでとりまとめ、実現へと進む流れを示します。日本創造学会の成果にも言及し、またChatGPTなどの生成AIを効果的に用いる方法も示します。
テキストは分かりやすい文章の読み物で、受講後にも引き続き復習と自主実習、発想実務の際の参考書として利用できます。資料として発想に役立つ考え方と発想のヒントを提供します。
*付録資料:
「発想に役立つ考え方のあれこれ」「汎用的に利用される概念集」「採用された開発テーマの公的資金申請書」「発想の実務における対応」など
○受講対象:
1.開発、技術、トラブル対応など種々の対象にアイデアが出ないとお困りの方
2.開発、設計、生産に携わって新しい展開を考えている方
3.発想の基礎から実用的な新しい方法まで学びたい方
○受講後、習得できること:
1.発想を訓練する方法と発想する力
2.アイデアにつながる多量のヒントの使い方
3.アイデアを実用化するための手順
4.常に発想するための意識の持ち方
<講演プログラム>
第1章 発想から実現へ
1. 技術活動には発想が必要
2. 新しいアイデアを生む守破離の流れ
3. 問題発見・課題解決と発想
4. 発想から実現への流れ
5. 創造性のレベルと訓練
第2章 発想の方法
1. 発想の基本
2. アナロジーは発想の宝庫
3. 発想法の分類
4. NM法
5. ヤング法「アイデアの作り方」
6. マンダラート
7. マインドマップ
8. シーズとニーズからの発想
9. 逐一反問法
10. オノマトペ感覚法
第3章 発想のヒント
1. ヒント連想の考え方
2. TRIZの発明原理
3. オズボーンのチェックリスト
4. 小波の追加リスト
5. 単位洗い出し法
6. 動詞連想法
7. 形容詞連想法
8. 接続語連想法
9. ことわざ連想法
第4章 発想のための基礎固め
1. 発想の基になる力
2. 発想するための姿勢
3. アイデアを出す環境づくり
4. 専門情報の収集と知識の獲得
第5章 アイデア創出の実行
1. 発想の下準備
2. コストの考慮
3. アイデアの出しあい方
4. 思いつきへの対応
5. 発想の範囲を広げる工夫
第6章 アイデアのまとめ方
1. 推論の型
2. 推論の進め方
3. ロジカルシンキング
4. KJ法で整理する
5. 概念を図示する
6. 文章にまとめる
7. アイデアを評価する
第7章 生成AIを利用した発想
1. 生成AIを扱う上での注意点
2. 意図に近い回答を引き出す工夫
3. アイデアを求めるための利用
4. 発想法と組み合わせたアイデア創出
第8章 まとめと勉強の方法
1. 各種の発想法の利用方法
2. アイデア創出から評価までの手順
3. 発想のための勉強法
<質疑応答>