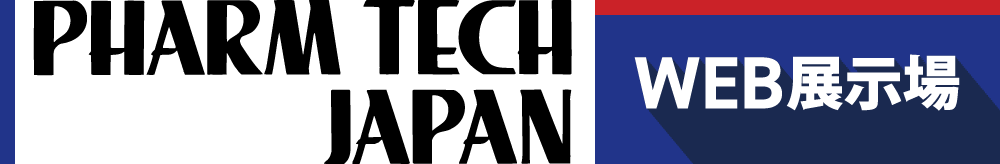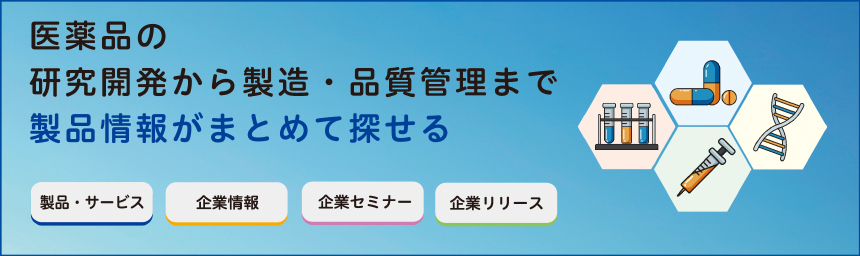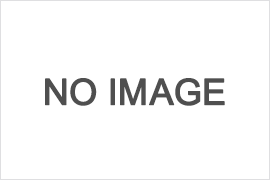キーワードから探す
カテゴリから探す すべてのカテゴリを見る
原薬・添加剤・中間体
製造機械・装置
物流・輸送
プロセス測定・検査
ラボ用測定・分析
滅菌・クリーン
供給・搬送
プラント・設備
包装関連
受託サービス
バイオ(抗体)医薬品
ITソリューション
コンサルティング・翻訳・その他
WEB展示場に出展中の企業・製品情報
注目の出展製品 すべての製品を見る
WEB展示場 出展企業 すべての企業を見る
【AD】~AI駆動型創薬の壁を乗り越える~ 標的の発見から臨床応用までの一貫したデータ活用と意思決定をサポート
10月2日、都内でCAS Life Sciences Summit2025が開催された。米国化学会を母体とするCASは化学物質に関する独自のデータベースや検索プラットフォームを提供し、科学の進展をサ ...続き 2025/11/17
【AD】柔軟性と経済性を両立 製薬合成向け水素化設備 最新撹拌装置とモジュール設計でラボから大型プラントまで対応
ドイツ・エカート社(EKATO Ruehr- und Mischtechnik GmbH)のDr. Peter Rojan氏(Head of Reactors &Process Plants ...続き 2025/11/26
最新業界トピック(ニュース記事の閲覧には会員登録【無料】が必要です。)
- 日本医薬品原薬工業会、ブラジル医薬品有効成分産業協会「ABIQUIFI」との交流強化へ 2025/12/10
- サンバイオ、「アクーゴ」の発売を見据え製造・品質保証体制を強化 生産本部長に元中外の磯野氏 2025/12/10
- BioJapan 2025 ライフサイエンス業界がコラボしたい業界は? BioJapanのLINK-Jブースアンケートで意識調査 2025/12/09
- PTJ編集長のコラム 医薬品のパッケージ開発のドラマを感じる 2025/12/09
- PTJ ONLINE WEBセミナー (WEBセミナー)バイオ医薬品のプロセス開発を成功させるカギとは? 2025/12/09
- 第44回 医薬品GQP・GMP研究会 関東甲信越ブロック、GMP調査における指摘事例の共通因子 2025/12/08
- 丸石製薬とムネ製薬、資本業務提携に向けて協議開始 2025/12/08