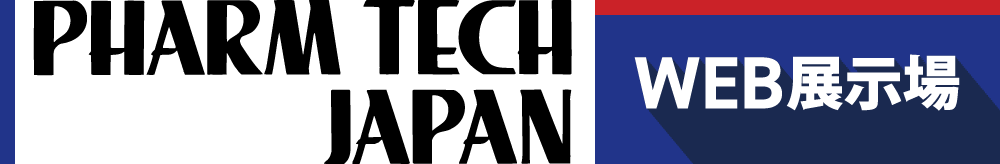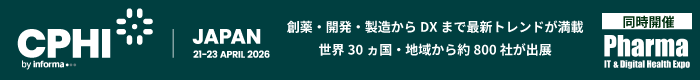| 開催日 | 2026年3月30日(月) |
|---|---|
| 開催地 | Web |
【開催日時】
2026年03月30日(月) 10:30~16:30
【講師】
京都大学総合研究推進本部 研究プロモート部門 副領域長 農学博士 岡本 昌彦 氏
ご専門:
有機化学,品質製造管理(医薬品/農業化学品),
計測科学,プロジェクトマネジメント,知的財産等
ご略歴:
住友化学(株)入社.同社の研究開発部門で医薬品(主として原薬),農業化学品,
機能性材料ならびに基盤技術開発(コーポレイト研究)などの研究開発に携わる.
医薬品分野では,特にCMC(Chemical Manufacturing Control)に従事.担当者,
マネジャー(課長・部長)として,IND申請・NDA用安定性試験,新薬の承認申請等を
経験.2020年4月より現部署(京都大学 総合研究推進本部).
【価格】
非会員: 55,000円 (本体価格:50,000円) 会員: 49,500円 (本体価格:45,000円)
会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円(税込)から
・1名で申込の場合、49,500円(税込)へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計55,000円(2人目無料)です。
【趣旨】
安定性試験の目的は,医薬品の品質,安全性および有効性を,その使用期限まで保証することにある.開発期間中の安定性試験結果は,承認申請医薬品の品質を把握するための重要な要素となる.これらが適切に実施されて,前臨床にはじまり第Ⅰ相からⅢ相までの臨床試験の治験薬の品質と,承認後に市場に供給される医薬品の品質の間に一貫性が確保されることになる.
医薬品の安定性試験の実施手順は,基本的に「ICH(Q1):安定性」の各種ガイドラインに基づく.しかし,開発期間中の安定性試験については,明確に設定されたガイドラインはなく,試験実施者の見識/経験等に基づく裁量に委ねられる部分が多い.開発期間中に生じる種々の問題に対処するためには,ICHガイドラインの原則を適切かつ柔軟に適用する必要がある.
本講演では,まず,現在,統合改訂が進められている,「ICH(Q1):安定性」の内容を紹介する.その内容を踏まえて,開発段階から新薬承認申請(NDA)に至る医薬品開発における安定性を担保するための安定性試験の設計(計画立案)の考え方や有効期間の設定について解説する.
また,安定性試験を実施する上で,重要な基礎データを与える,反応速度論(アレニウス・プロット)による安定性の予測についても説明する.
【プログラム】
1. 本講演の狙いと対象の医薬品
2.医薬品の開発と安定性試験の位置づけ
2-1.安定性試験の意義
2-2.医薬品の開発ステージにおける安定性試験の位置づけ
2 3.「ICH(Q1):安定性」ガイドライン
2-4.苛酷試験
3.安定性予測
3-1.安定性予測の目的と本講演での対象
3-2.従来知られている安定性の推定
3-3.反応速度論による安定性予測
3-3-1.研究の手順
3-3-2.反応速度に影響を及ぼす因子
3-3-3.Arrhenius Plotによる安定性予測
3-3-4.安定性予測の問題点
3-3-5.速度論的な取扱いでの注意点
3-3-6.活性化エネルギー測定上の,及びその評価に関する注意点
3-3-7.分解率を求める時の注意点
3-3-8.実用速度論
3-4.熱分析装置を用いた安定性予測方法
3-4-1.従来の安定性予測方法とその問題点
3-4-2.熱分析装置を用いた安定性予測のフロー
3-4-3.実施例
4. 安定性予測の新しい潮流-拡張Arrhenius 式による安定性予測
5.開発期間中に必要な安定性試験
5-1.処方開発・包材選択のための安定性試験
5-2.バルクホールド試験
5-3.輸送時・流通時の品質保証に必要な安定性試験
5-4.使用時の安定性試験
5-5.治験薬の安定性試験
5-6.新薬承認申請のための安定性試験
5-7.変更申請の際に必要とされる安定性試験
6.治験薬や新薬申請の安定性試験の基本的な考え方と有効期間の設定
6-1.安定性試験計画の考え方(6つのステップ)
6-2.一般的な要求項目(11個の検討要素)
6-3.有効期間の設定
7.安定性試験で必要とされる検討項目
7-1.バッチ及びサンプルの選択
7-2.測定項目
7-3.分析・試験方法
7-4.規格(項目と規格値)
7-5.保存条件
7-6.測定頻度(試験間隔)
7-7.保存期間
7-8.バッチ数
7-9.包装形態
7-10.評価
7-11.安定性情報・知見
7-12.安定性情報を得るための所要時間
8.まとめ
9.参考文献