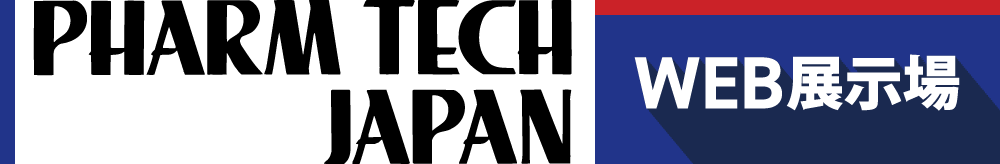| 開催日 | 2025年12月10日(水) |
|---|---|
| 開催地 | Web |
★「分析法バリデーションについて、基本から学びたい」という方へおすすめ。そもそもバリデーションとは?分析能パラメーターとは?分析法バリデーションに必要な「準備知識」から学ぶ基礎講座!
★高度な統計知識は本セミナーでは取り扱いません。電卓で計算できるレベルの簡単な演習問題を設けて理解できるような構成になっています。
★ICH Q2(R2)、ICH Q14で求められていることはなにか?から考え、しっかり基礎を固めます。
<新人・新任担当者必見!>
分析法バリデーションを行うための準備講座
~バリデーションの目的・意味/分析能パラメーターと各種試験/分析法開発の手順/ICH Q2(R2)、ICH Q14との関係~
<講師>
東京バイオテクノロジー専門学校 講師
帝京科学大学 生命環境学部 元 教授
(一社)医薬品適正使用・乱用防止推進会議 副代表理事 小島 尚 氏
<日時>
2025年12月10日(水) 10:30-16:30
<形態>
Zoomオンラインセミナー:見逃し視聴あり
<受講料>
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 56,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき45,100円
*受講料やセミナー申し込み~開催までの流れなど、詳細については、弊社HPのセミナーページを必ずご確認ください。
<セミナーポイント>
医薬品や化粧品、食品の試験では分析法バリデーションは不可欠な概念となっていますが、統計的手法を用いて計算するもの、敷居の高いものと受け取られることが少なくありません。また、分析法バリデーションの基礎知識について、必要性を感じながらもなあなあにしてしまっている、という声も寄せられています。本来、分析法バリデーションは試験法の分析過程を確認・保証するものであり、分析対象物に対してどのような分析ステップを組み立てていくべきか、なぜ、必要なのかなど、考え方から理解する必要があります。もちろん、統計学的手法は大切ですが、今回は深いところまでは触れず、電卓レベルの簡単な演習で理解できるように解説します。さらに、近いうちにStep5到達が期待されている「ICH Q2(R2)(分析法バリデーション)ガイドライン(案)」および「ICH Q14(分析法の開発)ガイドライン(案)」を参考に、今後の動向をふまえて解説します。この講座では分析法バリデーションをきちんとイメージできる”基礎”を身につけ、まず何から着手すればよいのかを理解し、自身で分析法を開発できるようになることを目指しています。
<講演プログラム>
<第一部> 分析法バリデーションを行うための準備
*化学分析におけるバリデーションを考える
1.バリデーションとはそもそも何か
・GMPにおけるバリデーションの位置付け
・バリデーションにおける文書
2.分析法バリデーションの目的
・分析過程の重要性
・試験方法への要求事項
3.分析方法が信頼されるための条件
・試験項目と装置、機材
4.必要な計算方法(必要な統計の基礎)
・電卓があればOK!基本的な考え方を解説
5.分析法の開発において考えるべきこと
・ICH Q2(R2),Q14で求めていること
・各段階におけるバリデーションの考え方
(開発段階、申請段階、再バリデーションが必要になる場合 等)
演習問題
<第二部>分析法の作成手順および分析能パラメーター解説
*分析法の開発における手順をわかりやすく図式で説明
1.特異性/選択性:試験法における最も大切な性質
・目的
・測定方法(LC、TLC、IR)
・特異性の検討
2.稼働範囲(直線性・範囲、検出限界・定量限界):検量線から定量する
・目的
・測定方法
・検量線の作成
・評価方法と判断基準の考え方
3.精確性(真度と精度):定量値の信頼性
・目的
・測定方法
・ばらつきと偏り
・室内再現精度の変動要因
・評価方法と判断基準の考え方
4.頑健性:条件のわずかな変動で測定値が影響を受けない能力
・変動因子① 種々の分析法に共通する変動因子
前処理、抽出操作等
・変動因子② クロマトグラフィの代表的な変動因子
HPLCの変動因子
GCの変動因子
TLCの変動因子
5.システム適合性試験:恒常的に分析を実施する
・目的
・必要な項目
演習問題
<第三部>各試験方法における分析法バリデーション
*製造承認書の規格及び試験方法における各パラメーターをとらえる
1.タイプⅠ(確認試験):有効成分を確認(定性試験)
最も基盤となる分析対象物の確認
2.タイプⅡ(純度試験):不純物や類縁物質を制御する
不純物の標準物質(品)が入手できるかで異なる対応
・定量試験
・限度試験
・標準物質
3.タイプⅢ(定量法):含量・力価を精確に求める
分析対象物は有効成分の含有量
演習問題
おわりに:参考
・分析技術の事例
・第18改正日本薬局方‐試験検査のバイブル
・第19改正日本薬局方原案作成要領
・記録の重要性
・不純物について
・汎用される分析手法
・HPLCの測定パラメーター
・参考となるガイドラインや関連通知
質疑応答