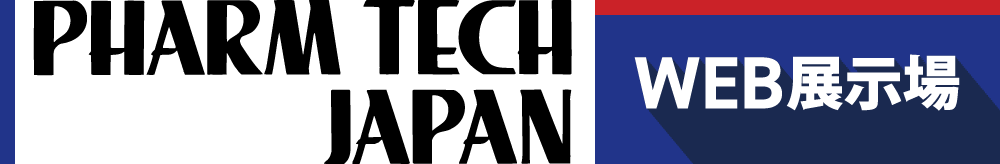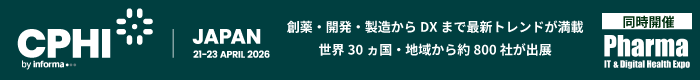| 開催日 | 2026年2月25日(水) |
|---|---|
| 開催地 | Web |
■講師
英二製剤研究所 代表 渡邊 英二 氏
【経歴】
テルモ株式会社にて44年間医薬品及び医療機器の研究開発、治験薬製造、製造工程設計に従事し、医薬品の固形、半固形、液剤の開発、体内埋め込み医療機器の工程開発・設計、原薬製造会社とのGQP契約等を担当し、2013年主席研究員にて定年退職、原薬管理および開発業務推進、後進の育成のために再雇用され2018年まで勤務した。現在、業界および学会活動を通じて医療製品の研究開発を支援している。
【研究・業務】
錠剤、軟膏剤、輸液、プレフィルドシリンジ、腹膜透析液、経腸栄養、人工赤血球、薬物徐放性ステント、癒着防止材等の設計開発・製造工程開発を行った。
【業界活動】
日本薬剤学会、製薬協品質委員、日本PDA製薬学会QAQC委員会、無菌製品GMP委員会、メディカルデバイス委員会の設立に参加、理事、MD委員会委員長などを歴任し、現在、日本PDA製薬学会特別顧問としてコンビネーション製品セミナーのコーディネートなどの活動をしている。その間、製薬用水の各条および参考情報の原案作成などにも参加した。2021年PDA本部(米国)Distinguished Service Award受賞。2023年日本PDA製薬学会川村賞受賞。
【専門】
医薬品・医療機器の開発・製造方法開発、レギュレーション
■趣旨
水道水(=常水)では、51項目ある試験項目が注射用水では4項目になっているのはなぜか?注射用水の製造で蒸留法の十分の一のエネルギーで製造できる超ろ過法とは何か?
製薬用水の品質確保のために必要なその製造方法とその原理、品質管理のための試験方法の設定の背景とその利用方法と限界を知る事により、効率的な製造とリスクの少ない品質管理手法を学ぶ。特に最新の製造技術および品質管理手法の進歩による効率的な製造・品質管理について理解する。
■プログラム
1. 製薬用水の規格と枠組み
・日本薬局方における製造用水の体系
・精製水・注射用水・常水(水道水)などの分類と規格
・バルク水と容器入りの違い
・製法(蒸留法・超ろ過法など)と選択基準
・純度試験項目の見直し、導電率・TOCの管理
2. 設備設計とバリデーション
・製薬用水設備の基本設計の留意点
・インラインモニターの活用
・バリデーション(DQ/IQ/OQ/PQ)と日常管理
・職員教育訓練の重要性
・無菌操作法に関する指針(改訂版)
3. 品質管理と試験法
・製薬用水の品質管理全般
・容器入り水の管理ポイント
・医薬品試験に用いる水の扱い
・微生物迅速測定法・MAT法などの最新技術
・SDGsの観点からの製法選定
4. 査察・トラブル・事例
・製造設備・サンプリング・品質管理に関する査察事例
・FDAワーニングレターの分析
・GMP事例集(2022年版)
5. 製薬用水に関するQ&A・参考情報
・RO膜・UF膜などの技術解説
・製剤総則事項