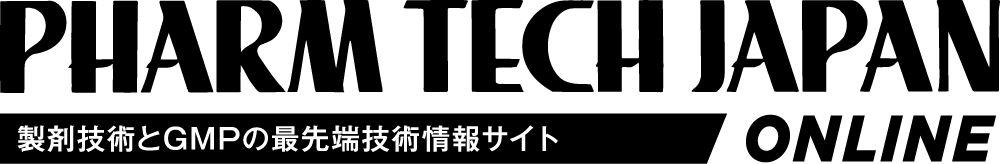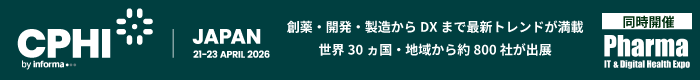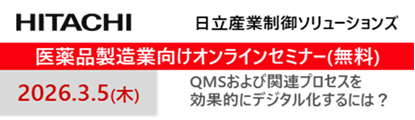ファームテクジャパン 2025年11月号 紹介
AIで変わる品質保証~規制動向と“信憑性”評価
PHARM TECH JAPAN 2025年11月号掲載のPHARM TECH JAPAN2025年11月号・特集「CMCにおけるDX導入のポイントと実践」でPMDA 上級スペシャリスト(品質担当)・松田嘉弘氏による寄稿『医薬品品質分野におけるAI技術の活用と規制』の内容を紹介します。
本稿では、医薬品の製造・品質分野におけるAI/機械学習(ML)の最新動向と規制の見取り図をわかりやすく解説しています。GMP違反やデータ改ざんの問題を受け、品質保証と効率化の同時達成が強く求められるなか、AI/MLは工程最適化、異常の早期検知(予知保全)、外観検査の高精度化、自動化による人的リスク低減、不正の未然防止など、多様なユースケースで価値を発揮し得ることを具体例とともに示します。とりわけ、デジタルツインを用いた開発・スケールアップの迅速化は、時間・コストの大幅削減に資する取り組みとして注目されます。
規制面では、FDAのEmerging Technology ProgramやEMAのQuality Innovation Group、PMDAの革新的製造技術対応チーム等が、産業界との対話を通じて導入障壁の低減と国際調和を推進。評価思想の中核にはASME V&Vの考え方があり、モデルに内在する不確かさ(UQ)を踏まえて「信憑性(Credibility)」をリスクベースで示すことが求められます。記事では、ICH Q8/Q9/Q10を踏まえたモデル分類の限界に触れつつ、ASME V&VやFDAドラフトガイダンスに接続する最新の評価枠組みを紹介します。
さらに、FDAが提案する“リスクに基づく信憑性評価”の7ステップ(QOIとCOUの定義、モデルリスク評価、計画立案・実行、結果の文書化、適切性の最終判断)を、図解とテキストで丁寧に解説。ブラックボックス化しがちなAI/MLモデルを、科学的根拠に基づいて適切に位置づける実務の道筋を示します。誌面の図2「リスクに基づく信憑性(Credibility)評価フレームワーク」は、導入検討から当局協議、バリデーションの文書化までの要点を一望できる構成です。
国内では、PMDAと国立医薬品食品衛生研究所、製薬各社、大学有識者、機器メーカーらが参画するAMED研究(2024~2026年度)が進行中で、AI活用の留意事項を文書化し、実装可能なコンセンサス形成を目指します。結びでは、連続生産など革新的製造技術とAIの融合がもたらす将来像――完全自動化や分散型製造の可能性――に触れ、産官学の連携とガイダンス整備を通じて、品質・有効性・安全性の一層の向上に貢献していく姿勢を示しています。
●見どころ
- 製造最適化・予知保全・自動化・不正防止まで、AI活用の実例を俯瞰。
- 規制当局の動向を整理(FDA ETT/EMA QIG/PMDAの取り組み)。
- リスクに基づく“Credibility”評価の7ステップを理解。
▶11月号の詳細はこちら
▶定期購読のお申込みはこちら