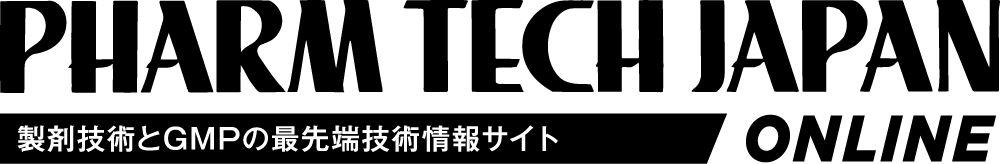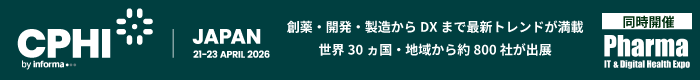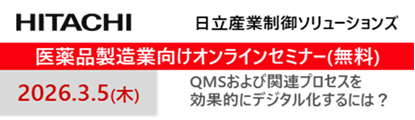ファームテクジャパン 2025年11月号 紹介
GMPの「センス」を鍛える SME育成で品質文化を強くする
PHARM TECH JAPAN 2025年11月号・GMPの本質に迫る人材の育成(センスを磨く)」の内容を紹介します。
●なぜ今、“センスある人材”が要るのか
本稿は、日本PDA製薬学会・関西勉強会(KSG)教育訓練グループが第31回年会で発表した内容を再構成し、「GMPの本質に迫る人材の育成」をテーマに、管理者やSME(Subject Matter Expert)の育成像を具体化したものです。品質問題や欠品、データインテグリティなど、近年の業界課題を踏まえ、単なる知識伝達ではなく「センスを磨く」視点から、人材に求められる資質と教育の在り方を示します。KSGは2023年に教育訓練グループを再始動し、GMP管理者・SMEの技量特定と育成方法の議論を本格化しました。
序盤では、原材料取り違えや計量ミス、ニトロソアミン、BCC汚染事例などの具体的リスクに触れ、欠品や回収の背景に人材・コスト・教育の不足が複合的に作用している現状を整理します。こうした環境下で、GMPをリードできる管理者と各分野のSMEに、従来以上の専門性・判断力が求められていることを強調します。
続いて、雇用の枠組み(メンバーシップ型/ジョブ型)が教育訓練設計や適格性評価に及ぼす影響を解説。職務要件を明確化し、事前研修と適格性評価を経た配置が、査察での説明可能性とPQSの信頼性向上に資する点を示します。さらにASTMやISPEの定義を踏まえ、分析・微生物・RCA・QRA、バリデーション、設備適格性など、医薬品分野のSME分類と役割・要件を体系化
中盤のハイライトは、SMEの判断過程の可視化です。知識・外部ネットワーク・経験という「引き出し」を状況に応じて取り出し、倫理と患者視点、企業理念を踏まえて最適解を導くプロセスを図示。三人のレンガ職人の寓話や、GMP啓発ビデオ「ステロイド47」を引きながら、目的理解に根差した“マインド”こそがセンスを下支えすると説きます。
後半は、センスを後天的に伸ばすための具体的トレーニングに踏み込みます。シミュレーションによるアクティブラーニング(医療・航空の例)や、逸脱・OOS・CAPAを題材とした社内外ワークショップにより、実務判断を鍛える方法を提示。加えて「失敗学」やジョブクラフティングを通じ、報告を促す心理的安全性と仕事の意義づけを高めるマインドセットを紹介します。最後に、教育プログラム設計と能力評価法の検討を今後の課題として掲げ、継続的な研鑽を宣言しています。
●見どころ
-
“センス”で挑むGMP:知識伝達を超え、倫理・患者視点を含む判断力の育成を体系化。
-
SMEを機能させる設計図:雇用形態と職務要件の明確化、ASTM/ISPEに基づく役割定義。
-
現場で効くトレーニング:シミュレーション/逸脱・OOS・CAPAワークショップで判断の実装力を強化。
-
マインドを育てる:「失敗学」とジョブクラフティングで報告文化と意義づけを醸成。
▶11月号の詳細はこちら
▶定期購読のお申込みはこちら