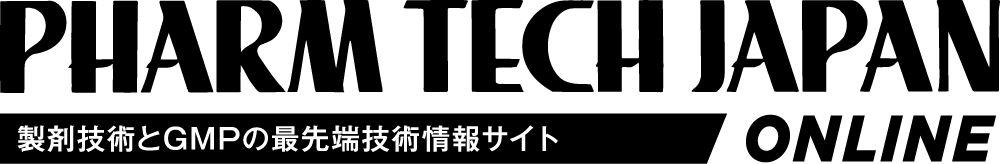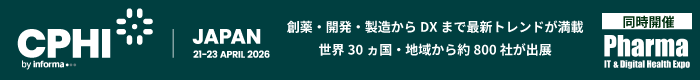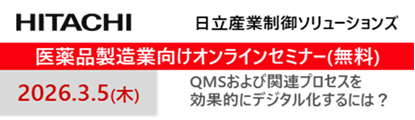ファームテクジャパン 2025年11月号 紹介
現場発DXで製剤開発を高速化—RPA×GAS×生成AI「RAG」でナレッジを力に
PHARM TECH JAPAN 2025年11月号・特集「CMCにおけるDX導入のポイントと実践」の「Sawai DX ~デジタル技術と相談支援型の生成AI開発による製剤開発効率化~」の内容を紹介します。
本稿では、沢井製薬の製剤研究部が進める“現場発のデジタル変革(DX)”を、具体的な成果とプロセスで紹介します。背景にあるのは、全国6工場で約800品目を担う供給責任と、従業員およそ3,000名の体制を支える開発現場の「安定生産と低コスト化」の両立という要請です。処方検討を担う同部では、“創造的検討時間の捻出”と“ナレッジの継承”を鍵に、頑健な設計を開発段階で構築する方針を明確化。紙・Excel中心の非効率や、報告書に埋もれる知見(サイロ化)といった課題を出発点に、現場自らデジタル活用の道を切りひらきました。
DXを阻む壁は「技術」「業務プロセス」「人」の3つ。最新ツール選定の難しさ、属人化した手順の温存、変化への抵抗感——これらに対し、同部は「小さく始める」を原則に、身近なRPAとGAS(Google Apps Script)で定型業務を一つずつ自動化。トップダウンではなく、意欲ある現場メンバーがボトムアップでDX推進チームを立ち上げ、業務棚卸し→自動化対象の分類→順次実装という小回りの利く進め方でブレークスルーを生みました。
成果は明快です。年間600時間以上の作業時間を削減し、研究者は“新しい処方を考える”本来業務に集中できるように。成功体験の共有を通じて意識改革が広がり、「60点でも早く楽にする」を積み重ねる文化が醸成されました。
次の一手が、生成AIを用いた「RAG(Retrieval Augmented Generation)」の内製導入です。キーワード検索では拾いきれなかった社内知見を“意味”で探索し、根拠リンク付きで即時に回答する“相談支援型”のエージェントを構築。初期リスクアセスメントでは、類似品の経験に加え、別領域のトラブル事例や解決策まで横断的に抽出でき、短時間で中立的・多角的な評価資料を作成できるようになりました。
運用面の工夫も特筆点です。Agentic RAGにより質問内容に応じた最適データソース探索を実装し、引用(根拠箇所)の即時確認でハルシネーションを抑制。現場主体のUI/UX設計で“使われるシステム”に仕上げ、部員の8割以上が利用、月平均50回超の定着に成功しています。
結論として、DX成功の鍵は「高度な技術」そのものではなく、“現場の主体性”と“小さく始める実装力”。本稿は、製剤研究の知識創造を加速し、安定供給に直結する「時間」と「ナレッジ」を生み出す実践記として、同業他社にとっても汎用性の高いベンチマークとなるはずです
●見どころ
- “小さく始めるDX”の実装論:RPA×GASでボトムアップに自動化、年間600時間超を創出。
- 相談支援型RAG:意味検索+根拠リンクで“ベテランに聞く”体験を再現、リスクアセスメントを高度化。
-
信頼性への配慮:Agentic RAGと引用表示で精度・透明性を担保、部員8割・月50回超が利用。
▶11月号の詳細はこちら
▶定期購読のお申込みはこちら