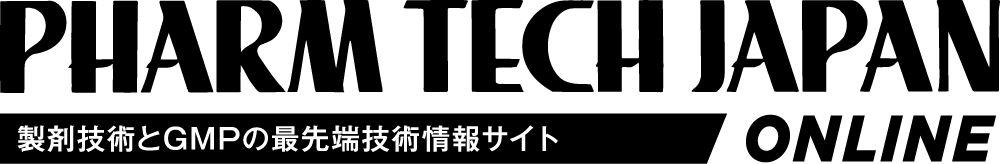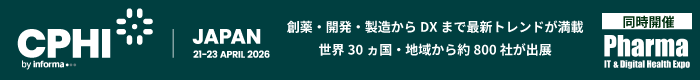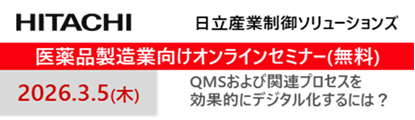─AD─
バイオ医薬品産業における人材育成と課題を考える
第24回メルクバイオフォーラム2025開催
メルク
メルクは2025年9月11日、「バイオ医薬品産業における人材育成と課題」をテーマに第24回メルクバイオフォーラム2025を東京コンファレンスセンター・品川で開催した。
フォーラムでは、バイオ医薬品業界の人材育成に焦点を当て、本領域のスペシャリストによる6講演が企画され、92社136人の参加者が聴講した。本レポートでは、同フォーラムのトピックを紹介する。
■バイオ人材育成は喫緊の課題
「バイオロジクスの製造・品質管理に関する人材育成の実践」と題する講演を行った神戸大学大学院特命教授・BCRET専務理事の内田和久氏は、「新型コロナ感染症発生時にワクチンが国内製造できないことがわかった」と切り出し、国内におけるバイオ医薬品への取り組みを振り返った。
2000年代はじめ、国内では抗体医薬の開発・製造が十分に行えなかったため、日本発バイオ医薬品創出を促進させべく、2012年3月に日本製薬工業協会の政策提言には、バイオ医薬品の開発・製造に携わる人材の育成、実用化促進、製造インフラの整備、承認審査・GMP適合性調査に関わる審査官や査察官の研修などが盛り込まれた。
こうした背景から、国内発となるバイオ医薬品の開発・製造にかかわる人材育成の拠点設立のため、一般社団法人バイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET)が2017年8月に誕生し、2018~2024年に200社以上、座学1703人、実習642人(PMDA60人含む)がトレーニングに参画した。
内田氏は、2025年7月に経済産業省が再生医療等製品を円滑に製造できる能力を国内に確保するため、①CDMOの国内受託製造拠点の整備や製造人材育成に対しての支援を行ったこと、②厚生労働省もワクチン生産体制整備や次世代バイオ医薬品等創出に向けた人材育成支援事業の展開など、CMO・CDMO含めてバイオロジクスの製造設備の充実を図っている現状を紹介。一方で、「GMP人材育成には、製薬企業やCDMOなどの製造現場が必要であり、人材育成には1年程度は必要」と述べた。
また、海外の人材育成組織の先進事例として、公的資金が投入されている米国Biomanufacturing Training and Education Center (BTEC)、アイルランド National Institute for Bioprocessing Research & Training(NIBRT)のバイオ医薬品の教育システムを紹介。国内においてもBCRETが中心となり富山県立大学、東京薬科大学、山口東京理科大学などと連携、さらにパーソルテンプスタッフと“バイオ医薬品に特化した技術者を育成する研修”について業務提携を行うなど、バイオ人材育成に取り組んでいることなどを明かした。
「近年、薬学部を中心にバイオ医薬品人材を輩出したいというマインドセットになってきている。ただ、CMCの部分がボトルネックになっている。CMCがなければ始まらない。アカデミアの有望なシーズの実用化に向けたトランスレーショナルリサーチでは、不明確な点が多い。CMC人材をはじめ、バイオロジクス人材育成は重要である。複数業界からなるステークホルダーが連携し、CMC技術やGMP製造などの共有化が可能な部分を非競争領域としてはどうか」と提言した。
■各社の工夫を凝らした人材育成の取り組み
「協和キリンにおける人材育成の取り組み」のタイトルで講演した協和キリンの髙藤修平氏は、2025年3月に竣工した原薬製造棟(HB7棟)内にあるバイオ医薬品製造や品質管理作業のトレーニング施設における主要な製造プロセスについて、自社の製造現場と同じ操作やシミュレーション作業を行っていること、実技と座学を組み合わせた育成プログラムを充実させるなど、人材育成強化を図っていることを紹介した。
「中外製薬工業における人材育成の取り組み」と題して講演した中外製薬工業の磯野哲也氏は、バイオ医薬品産業における人材不足に対して、①アカデミアへのGMP教育資料作成支援、②バイオ医薬品開発・製造の高度生産技術に関わる人材育成プログラム開発、③人材育成ニーズ把握のためのタレントポートフォリオのフレーム作成、④実生産設備を利用した実践的技術研修に取り組んでいることなどを紹介した。
「AGCネットワークを活用した人財育成の取り組みと挑戦」と題して講演したAGCの高見潤氏は、同社の国内外のネットワークを活用して、それぞれの拠点の強みを生かし、社員を派遣して研修することで、技術習得・技術移転をしていると説明。「モダリティも拡大しており、人財育成は急務。グローバルCDMOとしての日本のプレゼンスを確立させ、お客様から最初に声がかかるCDMOサービスの提供者となる」との意気込みを述べた。
「CMC薬事業務のパラダイム転換と専門人材育成の課題」と題して講演した第一三共の平澤竜太郎氏は、CMC技術と薬事規制の両方に精通した人材の必要性を述べ、規制当局との合意形成をサイエンスに基づいて合理的に進められる人材の育成は重要課題であると指摘。「CMC薬事には、サイエンスの本質的な理解が求められる。直接的なよりどころがない状態で、ストーリーを紡ぎながら合理的な判断をするスキルを磨くべきである。ライフサイクルを通じて生じるさまざまな課題に、いかに先回りして対応できるかが重要である」と強調した。
■GMP教育は未来への投資
「我が国のGMP人材育成の課題と今後の在り方」と題して講演した東京理科大学の櫻井信豪氏は、昨今のGMP違反事例について触れ、GMPが形骸化していないかとの警鐘を鳴らした。櫻井氏はその背景として、①生命関連品をつくっているというコンプライアンス意識の欠如、②教育・育成の不備、③薬学部でGMP教育が皆無であること、④日本の市場出荷判定の仕組み、⑤現場にいない状況でのQA育成は困難、⑥20年前の制度の有効性の検証が必要性であることを挙げた。
海外事例として、アイルランドでは人口550万人の1.6%にあたる85,000人が製薬企業の従業員として従事し、高度なスキルと技能を有する人材を潤沢に確保していること、NIBRTが効果的に機能し、卓越した品質教育を行い、出荷判断にあたって“意思決定が患者優先でできるか”を徹底的にトレーニングしていることを紹介した。
櫻井氏は日本のGMP教育の課題として、①薬学教育にGMPを取り入れる、②QP相当育成コースの設置、③多くの企業が活用できる体系的な教材作成、④教員養成コースの設置を挙げた。
「GMP教育は、単なるオペレーター教育ではない。ルールを正しく理解して科学的な視点で製造の恒常性や品質保証を実施する。その根底にあるのは、患者ファーストの精神。リスクベース思考と自律を意識した教育を行い、その手順をなぜ守るのか、逸脱したら何が起こるのかを理解して、自ら判断して行動できるようにすべき。GMP教育は未来への投資。現場で生きる教育こそが企業を強くし、安定供給と品質保証を支える力となる」と強調した。
講演後のパネルディスカッションでは、登壇者を交えバイオ人材育成への取り組みの課題や業界団体の取り組みなどについて熱い議論が交わされた。
●製品に対するお問合せはTech4U_JP@merckgroup.comへおねがいします。
●その他の製品についてはこちらをご覧ください。
■お問い合わせ
メルク株式会社 プロセスソリューションズ事業本部
〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JP タワー
TEL:03-4531-1143
URL:www.merckmillipore.jp