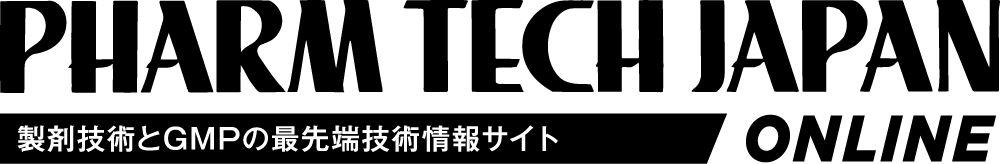9月12日(日)~14日(火)
第10回DIA 臨床研究・医薬品開発に必要な生物統計ワークショップ
●開催趣旨
医薬品の開発や審査、あるいは育薬といった医薬品の評価に関わる日々の業務の中で、統計について疑問に思っていることはありませんか?また、論文や報告書を読む際に統計用語や統計的な結果の解釈が分からないと思うことはないでしょうか?日々の業務の中で、生物統計担当者の言っていることや意図していることがよくわからないけれど、いまさら聞けないということも少なからずあると思います。
統計手法、試験デザイン、必要症例数、治療の割付け、バイアス、試験結果の解釈、欠測値への対応、中止脱落の治験への影響、検定の多重性など、医薬品の評価に関して統計学が関与する範囲は非常に広く、そうした幅広い知識を身につけることは容易ではありません。「臨床試験のための統計的原則」の補遺ICH-E9(R1)では、試験計画時に試験の目的、対象集団、エンドポイントに影響する中間事象やその扱いなどを議論し、その試験のデータから推定すべきものをEstimandとして試験計画書に定義することが新たに求められていますが、こうした統計関連のガイドラインを適切に理解し、それを実践するためには、相応の統計的な知識が必要となっています。
臨床試験を実施する立場ではなくても医薬品の評価に関っていれば、公開されている添付文書、審査報告書、CTD、論文、広告資材、インタビューフォームなどの文章や図表をしばしば目にする機会があると思います。ひとつの臨床試験の中でも、多くの種類のデータが収集され、さまざまな統計解析が行われますが、検定のp値や信頼区間が提示されているからといって、それらの解析結果を鵜呑みにしてよいとは限りません。医薬品評価では、統計的コンセプトを踏まえて、臨床試験から得られるデータそのものについてじっくり検討し、確かな推論を行うことが、より良い意思決定や議論に寄与します。このような作業は、生物統計家と他の非臨床や臨床の専門家が互いの専門性や考えを理解し合った上での協業が必須になります。生物統計家と他の専門家との適切な協業関係を構築するには、生物統計以外の専門家の方々も公開されている資料や論文から、臨床試験の結果を正しく理解できることが不可欠です。そこで本ワークショップでは、医薬品評価に関わる「生物統計を専門としない方」を対象に、統計的コンセプトをご理解頂くためのオンラインワークショップを開催いたします。まず、1日目は、ちょっと自信のない方向けに、統計学の基礎的内容を説明する基礎コースを開催いたします。基礎コースでは、「2020年版医薬統計ポケット資料集 第4部:初学者のための医薬統計講座」で示されている内容に沿って基礎知識を丁寧に説明いたします。このポケット資料集は教材として参加者全員に配布し、本オンラインワークショップでも取り上げる予定です。
2日目は、医薬品評価での基本的な統計の原理、試験デザインやEstimandについて解説し、症例数設計を題材にモンテカルロシミュレーションの概念を体感していただきます。その上で、広告資材等に結果を提示する際に必要な検定の多重性について概説します。
3日目は、PMDAの立場から医薬品の承認審査の際に考慮される臨床試験のデザインと結果の考察について解説します。また、グループワークでは、本ワークショップの内容を踏まえた具体的な事例を紹介し、その事例に沿った試験の計画や結果の解釈に関する課題を数名のグループで議論してもらいます。グループワーク中は、講師陣がファシリテータとして、皆様の議論をサポートいたします。講師陣のアドバイスを受けながら、グループ内でいろいろと意見交換することで、本ワークショップの内容をより深く理解することができますので、参加された皆様が、臨床試験の計画を立案し、論文等で公表されている臨床試験データを解釈する際に大変役立つ内容となっています。最後に、本コースの仕上げとして、試験結果のエビデンスの重み、エビデンスの補強の仕方について解説します。
以上のように、本ワークショップは医薬品開発に必要な統計的観点や統計解析結果の解釈を今一度見直していただくという点で、生物統計を専門としない方に大変有益な内容となっております。生物統計の知識は必要だけれども、なかなか学ぶ機会がないという方は、ぜひご参加ください。なお、本オンラインワークショップは日本語で行います。
●開催概要
日時:2021年9月12日(日) 13:00-17:30 基礎コース
2021年9月13日(月)~14日(火)
会場: WEB開催( Zoom)
申し込み・詳細:https://www.diaglobal.org/Tools/Content.aspx?type=eopdf&file=%2fproductfiles%2f9683674%2f21308%2Epdf
●プログラム
1日目 : 9月12日(日) 基礎コース
13:00-17:00 生物統計学の基本を見直そう:ワークショップ前の基礎コース
(途中、2回ブレイクあり)
講師: 東京大学 大庭 幸治
・ 記述統計:データの把握
・ 推測統計:点推定と区間推定
・ バイアスとバラツキ
・ 推測統計:点推定と区間推定
・ 仮説検定を用いた判断
・ 例数設計の概念
臨床試験では研究計画から結果の解釈、説明に至るまで統計学を避けて通ることはできません。一方で、統計学を学びたい、学んでもすぐに忘れてしまうといったお話もよく耳にします。このような方々のために、初学者のための生物統計講座として、1日目に基礎コースとしての講座を設けました。2日目以降、様々な応用事例が出てきます。そこで用いられる統計手法や統計的な考え方の基礎についての予習となる内容ですので、この基礎コースで基本をしっかりとおさらいしてください。講演は会期1週間前より録画を配信し、質問を受け付けます。当日の講演で内容の詳細について解説し、質問にも丁寧に回答いたします。テキストには、2020年版医薬統計ポケット資料集「第3部:初学者のための医薬統計講座」を用います。統計の基礎を学びたい方、2日目以降の理解を深めたい方は3日間通しでの受講をお勧めいたします。
17:00-17:30 Q&A と総括
2日目 : 9月13日(月)
9:30-9:45 開会の挨拶と趣旨説明
9:45-12:40 臨床試験で典型的に用いられる統計手法と試験デザイン ~ポイント解説~
(途中、ブレイクあり)
講師:東京大学 上村 鋼平
北海道大学病院 伊藤 陽一
• 試験のタイプ(優越性試験、非劣性試験)
• 点推定と区間推定
• 仮説検定と症例数設計・P値・検定の過誤・多重性
• バイアスを取り除くための工夫(ランダム割り付け、盲検化、etc)
• 臨床試験におけるバイアス
• ランダム化の手法と盲検化
• 解析の事前規定と盲検下レビュー
• 試験対象集団
• Estimand
本セッションでは、臨床試験の計画や実施に関わる方であれば、必ず知っておくべき常識的な試験デザインの知識や典型的に用いられる統計手法のポイントを広範囲にわかりやすく解説します。具体的には、治験治療群と対照群の比較可能性を保証するためのランダム化の手法と臨床試験の実施にかかわるバイアスを防ぐための盲検化、統計解析に関連する解析の事前規定と盲検下レビュー、解析対象集団、Estimandといった内容です。実際に臨床試験を計画する際にはさまざまな議論が行われますが、これらの基本的な事項を適切に理解しておくことは、担当者間のコミュニケーションを円滑にするだけでなく、実際の業務の中で発生し得るイレギュラーな議論や問題事例へ対処する際にも役立ちます。また、本セッションは、ワークショップの全体像を俯瞰する内容となっており、ワークショップで学ぶ応用事例を含めた内容により、さらに上記の項目の理解を深めていただけるものと思います。
ランチブレイク
13:40-14:55 モンテカルロシミュレーション の概念と例数設計を体感する
講師: ヤンセンファーマ株式会社 宮里 盛幸
近年、いろいろな場面で”シミュレーション”という言葉を聞きます、最近だと新型コロナウイルス関連でも飛沫や感染状況について良く聞くようになりました。臨床試験の計画も複雑な試験デザインが多くなってきたこともあり、様々な想定の下でシミュレーションを行い、その挙動や算出された成功確率に基づいた検討を行うことがより重要になってきています。被験者数設定の検討はその活用例の一つです。本セッションでは、モンテカルロシミュレーションを概念的に体感して頂き、例数設計の実際を少しご紹介します。
15:05-16:35 臨床試験における検定の多重性
講師: 横浜市立大学 坂巻 顕太郎
いくつかの試験結果から「都合のよい」結果を恣意的に選択することは、誤った情報に基づいて開発を進めたり、宣伝したりする可能性を高めます。これは多重性に起因する問題です。 医薬品の承認申請において、検証試験で生じる多重性は調整が必須と考えられています。また、企業が広告資材に試験結果を提示する際にも、多重性に対する理解が必要になってきています。本講義では、サブグループ解析や複数の評価項目の解析などの多重性が生じる状況や多重性の問題を説明し、第1種の過誤確率と検出力への影響を説明します。また、検定の多重性への対処方法として、古典的な方法からゲートキーピング法までを概説します。
16:35-16:50 Q&A と総括
3日目 : 9月14日(火)
9:30-10:45 臨床試験のデザインと結果の考察 ‐医薬品の審査・相談業務の経験から‐
講師:独立行政法人医薬品医療機器総合機構 菅野 弘美
本セッションでは、医薬品開発において統計学の考え方が実際にどのように活かされているのかについて、規制当局の観点から、審査の実例を用いて紹介します。 Estimand と臨床試験のデザインとの関連についても考察します。今後のよりよい開発計画の立案に向けて、生物統計以外のご専門の皆様と生物統計担当者との間の相互理解を促すことを目的としています。
ブレイク
10:55-15:20 グループワーク
講師:第一三共株式会社 小山 暢之
第一三共株式会社 大和田 章一
第一三共株式会社 菊森 久仁佳
興和株式会社 菅波 秀規
ファイザーR&D合同会社 荒川 明雄
ファイザーR&D合同会社 吉山 保
審査報告書等に公表されている臨床試験結果の実例を利用して、臨床試験のデザインや結果の統計的な解釈について少人数のグループで議論し、 それまでの講義内容について理解を深めます。特に Estimand に関して、実際の臨床試験でどのように定義すればよいのか、実例に基づく課題をグループで議論することで学んでいただきます。なお、議論の対象とする実例および議論する課題については事前にお送りする資料でご確認いただきます。グループワーク・AM ※グループワークに必要な知識のおさらいとグループワークに用いる実例の紹介、課題提示を行います。
ランチブレイク
13:00-15:20 グループワーク・PM A
※午前中のセッションで出された課題について、グループワークを行います。
グループワーク中は、適宜、講師が各グループの議論に参加して、議論を盛り上げます。
ブレイク
15:30-16:40 その結論、述べる前に考えて!
講師: ファイザーR&D合同会社 小宮山 靖
統計解析の結果を結論の拠り所にしていませんか?エビデンスの強くない結果を示し、「統計的有意差が認められた。」で済ませていませんか?本コースの仕上げとして、エビデンスの重み、エビデンスの補強の仕方について考えてみましょう。
ブレイク
16:50-17:05 Q&A と総括