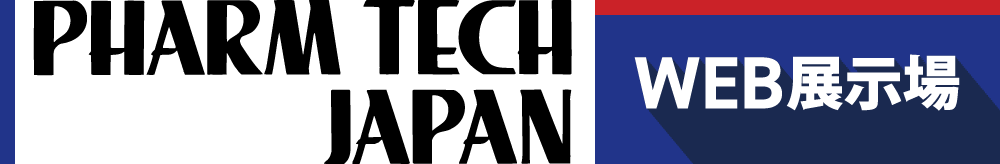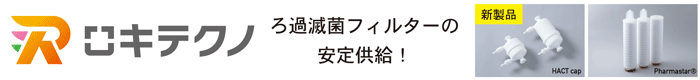| 開催日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 開催地 | 東京都 |
講師 宮崎大学 農学部 農学科 海洋生命科学領域 教授 博士(水産学) 田岡 洋介 氏
●日時:2026年1月14日(水) 10:30-16:30 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。
●会場:[東京・東陽町]江東区産業会館 2階第2会議室
■はじめに
水産増養殖における魚病被害額は国内では100億円に達し、世界規模では60億米ドルの経済的損失をもたらしていると言われてます。一方で、抗生物質の使用による対策では薬剤耐性菌の問題が懸念されており、薬剤に頼らない防疫技術の開発に注目が集まっている。そこで本セミナーでは、水産増養殖におけるプロバイオティクスの有効性に関する知見を紹介し、その可能性について解説するとともに、具体的なスクリーニング法についても概説する。また近年「マイクロバイオーム」が宿主生物の健康状態に密接に関係することが明らかとなって来た。魚類におけるマイクロバイオーム研究の最新の知見を口述するとともに、特に腸内フローラが魚類の免疫応答に及ぼす影響ついても解説する。
■想定される主な受講対象者
・水産養殖における防疫技術開発にご関心のある飼料メーカーの方
・プロバイオティクス製剤を開発されたい飼料メーカー、R&D部門の方
・薬剤を用いない防疫技術に関心のある養殖業者の方
・本研究室で見出した新規プロバイオティクス乳酸菌 K-C2株の製剤化にご関心のあるメーカーの方
・大学での微生物製剤の評価依頼を検討されているメーカーの方
■必要な予備知識
・微生物学の基本的な知識(分類や細菌の取り扱いの方法など)
※必須というわけではありません。講義で補足しますが、講義内容をイメージしやすく、また理解しやすいかと思います。
■本セミナーに参加して修得できること
・水産増養殖の現状と課題
・腸内細菌とホスト(宿主生物)との関係、および免疫応答
・薬剤に頼らない「プロバイオティクス」の防疫技術(基礎的知見と最新の研究事例)
・養殖におけるプロバイオティクスのスクリーニング法とその作用メカニズム
・陸上養殖における細微生物ローラの役割
1. 水産業の現状
1)獲る漁業と養殖業の国内外の動向
2)水産増養殖における魚病とその対策
3)養魚用飼料の基礎と問題 ~魚粉代替飼料の開発~
4)養殖と水環境
2. 腸内細菌と宿主
1)腸内細菌の役割
2)腸内細菌と物質代謝 ~微生物相互作用と脳腸相関~
3)食と腸内細菌
3. マイクロバイオームとヴァイローム
1)体全体を覆う微生物たち
2)微生物叢と宿主の免疫応答
3)魚類におけるマイクロバイオーム像
4. プロバイオティクス候補のスクリーニング法
1)プロバイオティクスの基礎知識
2)スクリーニング法 ~in vitro系とin vivo系~
3)プロバイオティクスの培養法と製剤化
5. 水産増養殖におけるプロバイオティクス研究の最前線
1)プロバイオティクス研究の歴史
2)生菌体プロバイオティクスと死菌体プロバイオティクス
3)プロバイオティクスと物質代謝
4)プロバイオティクスと魚粉代替飼料
6. 陸上型閉鎖養殖システム(RAS)とプロバイオティクス
1)RASの構造と特徴
2)RASにおける微生物の役割・動態
3)RASにおける生菌剤利用の可能性
7. 水産増養殖における新規プロバイオティクス Lactococcus lactis subsp.lactis K-C2株に関する研究会開発
1)プロバイオティクス候補のスクリーニング
2)in vitro試験によるプロバイオティクスの評価
3)in vivo試験(飼育試験)によるプロバイオティクスの評価
8. 市販プロバイオティクス製剤の評価試験 ~産官学共同研究の事例~