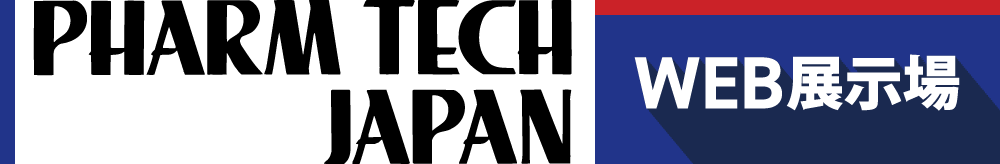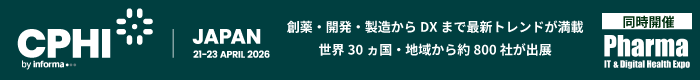| 開催日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 開催地 | Web |
★生成AIを“使う人”から、GMP領域で実践的に“活かす人”へ
■セミナーテーマ
GMP管理における生成AI活用入門
■講師
(株)EQUES 代表取締役 CEO 岸 尚希 氏
■主経歴等
東京大学大学院情報理工学研究科。元松尾研究所プロジェクトマネジャー。
松尾研起業クエスト1期生。松尾研究所チーフAIエンジニアとして企業との共同研究に従事。
その後、現実世界と情報学の融合を志し、東京大学工学部計数工学科在学時にEQUESを創業。
■専門および得意な分野・研究
システム情報学、特にテラヘルツ波通信とハプティクス(触覚技術)。
●日時:2026年2月18日(水) 13:00-15:30 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
■講座のポイント
本講演では、AIの基本概念から製薬業界での実践活用までを体系的に解説します。まずAI・機械学習・深層学習の定義と問題設定を整理し、第一次~第四次AIブームを振り返りつつ、生成AIと言語モデルの進化を概観します。続いて、創薬・CMC・臨床・品質保証など、医薬品ライフサイクル全体に広がる国内外のAI活用事例を紹介。特に生成AIの普及状況と、技術・倫理両面での課題を整理します。そのうえで、RAGやMCP/A2Aといった次世代技術が課題解決をどう支えるかを解説します。さらに、「AIが人を置き換えるのではなく補完する」視点やスモールスタートの重要性を強調し、品質・製造・出荷管理におけるAI応用事例を提示します。GMPの現場でAIを単なるツールとしてではなく、品質と効率を両立させる実践知として使いこなす人材への進化を目指します。
■受講後、習得できること
1.AI・機械学習とはそもそもどういったものなのか、これまでどんな進歩を経てきて今後どのように発展していくのか、を理解することができる
2.現在のAIの技術レベルで、品質保証の分野を中心に、現場でどのようなことができるようになるのか、活用のイメージを持つことができる
3.AIの今後の発展を踏まえ、将来的にGMP領域における業務をどのような形にしていくべきか、戦略検討の技術面の足がかりを得ることができる
■講演プログラム
1.AIの概要
1.1 AI、機械学習、深層学習の定義
1.2 機械学習の問題設定のイメージ
2.AIの歴史
2.1 第一次~第四次人工知能ブーム
2.2 生成AIの出現
2.3 言語モデルの仕組み
3.製薬業界におけるAI関連の事業展開
3.1 海外事例
3.2 国内事例
4.医薬品業界におけるAI活用関連のニュース
4.1 創薬の加速、CMCプロセスの短縮、研究者の生産性向上
4.2 臨床開発業務におけるAIエージェント活用
5.生成AI活用の状況
5.1 日本国内における生成AIの利用状況
5.2 米国における生成AIの利用状況
6.生成AI活用の状況
6.1 AI活用の技術的課題
6.2 AI活用の倫理的課題
7.AI活用の課題を乗り越えるための技術的な解決策
7.1 RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)
7.2 MCP (Model Context Protocol) と A2A (Agent‑to‑Agent Protocol)
8.AI活用の課題を乗り越えるためのマインドセット
8.1 AI活用と人の役割
8.2 スモールスタート
9.AI活用の事例
9.1 品質マネジメント×AI
9.2 製造工程管理×AI
9.3 出荷管理×AI
10.QAIの紹介
10.1 製薬品質保証の文書業務効率化SaaS
10.2 変更管理業務等での文書作成補助
10.3 医薬品に関する機密情報を用いた製薬特化LLM
11.生成AI活用の実現に向けて
11.1 伴走型開発支援
(質疑応答)